訪問調査で決まる介護サービスの未来
介護が必要な高齢者やそのご家族にとって、介護保険制度は生活を支える大切な仕組みです。その中でも「訪問(認定)調査」は、介護サービス利用の要となる「要介護度」を決める重要なステップです。認定調査員が自宅や施設を訪れて行うこの調査は、約1時間かけて本人の心身の状態を詳細に把握し、適切な支援が受けられるかどうかを判断します。
しかし、多くの方が訪問調査の内容や流れ、どんなことを伝えればよいか分からず不安を感じています。特に本人が普段通りにできないことを無理に見せたり、逆にできることを過小評価したりすると、正しい要介護度判定につながらない恐れがあります。
「介護保険制度の訪問調査とは何か」「認定調査員はどんな項目をチェックするのか」「調査時に気を付けるべきポイント」など、初めての方にも分かりやすく解説します。さらに申請から判定までの流れや再申請・不服申し立て方法も詳述し、ご家族が安心して手続きを進められるようサポートします。
介護保険制度 訪問(認定)調査とは?
訪問(認定)調査の目的
介護保険制度では、高齢者がどれだけ日常生活で支援や介助が必要か「要支援」「要介護」の度合いによって判定されます。この判定に欠かせないのが、「認定調査員」が本人宅や施設へ訪問して行う聞き取り・観察調査です。ここで得た情報をもとに専門家による審査会で最終的な要介護度が決まります。
認定調査員とは?
市町村から委託された専門資格者であり、高齢者本人や家族から生活状況・身体機能・精神状態など多角的に聞き取ります。また主治医意見書も併用し、公平で正確な判定資料作成に努めます。
訪問調査の流れ
- 申請受付
市町村役場等へ要介護認定申請書提出。 - 日時連絡
後日、認定調査員から訪問日時連絡あり。体調不良時は再設定可能。 - 訪問面談
本人および家族立ち会いのもと約1時間程度実施。 - 基本調査と特記事項記入
74項目ほどある「基本調査」票に沿って回答収集し、必要に応じて具体的状況を文章化(特記事項)。 - 主治医意見書取得
医師から医学的意見書を取り寄せる。自己負担なし。 - 一次判定と審査会判定
コンピューターによる一次判定後、専門家審議による二次判定で最終決定。 - 結果通知
申請後30日以内に郵送通知される。
調査項目例
- 身体機能:歩行能力、起居動作、排泄管理など
- 生活機能:食事摂取状況、更衣、入浴など
- 認知機能:記憶力、意思伝達能力
- 精神・行動障害:被害妄想、大声発声など
- 社会生活適応:金銭管理能力、薬服用管理
- 特別医療ケア:点滴管理や人工呼吸器使用等
調査時の注意点
- 本人が無理して普段できないことを見せたり、「できる」と嘘をつくことは避けましょう。
- 家族や普段関わる人が立ち会い、「ありのまま」の状態や困っていることを具体的に伝えることが重要です。
- 「浴槽入浴には2人必要」「夜間徘徊で家族不眠」など具体例を書いたメモや「介護日誌」があると説明しやすいです。
- 曖昧な表現は避け、「食事したこと忘れて催促する」など詳細に伝えましょう。
申請前・認定前サービス利用について
結果待ち期間でも条件付きでサービス利用可能ですが、不適切利用すると自己負担増加となりますので注意してください。地域包括支援センターやケアマネジャーへの相談がおすすめです。
以下に、介護保険の認定調査員による基本調査項目を分かりやすい表形式でまとめました。各群ごとに項目を整理し、「内容説明」「調査項目」「回答形式」なども明記しています。
| 群別 | 項目分類 | 内容説明 | 調査項目(代表例) | 回答形式・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第1群 | 身体機能・起居動作 | 高齢者の身体的な動作能力や筋肉の状態を評価。まひや拘縮の有無、基本的な動作能力を確認。 | ・まひの有無(左右上肢・下肢など複数回答可) ・拘縮の有無(肩関節、股関節、膝関節など複数回答可) ・寝返り ・起き上がり ・座位保持 ・両足での立位保持 ・歩行 ・立ち上がり ・片足での立位 ・洗身 ・爪切り ・視力 ・聴力 | 「できる」「一部ならできる」「できない」など択一式。複数回答可の項目あり。 |
| 第2群 | 生活機能 | 日常生活に必要な基本動作や介助状況を評価。どこまで自立しているか、どんな介助が必要かを把握。 | ・移乗(ベッドから椅子などへの移動) ・移動(歩行や車椅子使用等) ・嚥下(飲み込み) ・食事摂取 ・排尿 ・排便 ・口腔清潔 ・洗顔 ・整髪 ・上衣の着脱 ・ズボン等の着脱 ・外出頻度 | 択一式。「できる」「一部ならできる」「できない」等で評価。 |
| 第3群 | 認知機能 | 認知能力や記憶力、理解力を評価。意思伝達や時間場所認識など日常生活に必要な認知状態を確認。 | ・意思の伝達能力 ・毎日の日課理解 ・生年月日や年齢を言うことができるか ・短期記憶(直前に何をしていたか思い出す) ・自分の名前を言うことができるか ・今の季節理解 ・場所理解(自分がいる場所を答えられるか) ・徘徊(目的なく歩き回るか) ・外出時に戻れなくなるか | 択一式で評価。 |
| 第4群 | 精神・行動障害 | 認知症などによる精神面および行動面の障害有無と程度を評価。被害妄想、感情不安定、暴言暴力等も含む。 | 1. 物盗られ妄想など被害的になる 2. 作話(事実と異なる話) 3. 感情不安定(泣く、笑う等) 4. 昼夜逆転 5. 同じ話を繰り返す 6. 大声を出す 7. 介護抵抗する 8. 家に帰ると言い落ち着かない 9. 一人で外出したがる、目が離せない 10. 無断で物を集め持ってくる 11. 物壊しや衣類破損行為 12. 重度物忘れ 13. 意味なく独り言や独り笑いする 14. 自己中心的行動する 15. 会話が成立しないほど話がまとまらない | 各症状の有無について「ある」「なし」等で判断。 |
| 第5群 | 社会生活への適応 | 地域社会で生活するために必要な能力と介助状況を評価。金銭管理や薬服用、買い物等の日常意思決定も含む。 | 1. 薬の内服管理能力 2. 金銭管理能力(支払い等) 3. 日常的意思決定能力 4. 集団への適応状況(不適応は問題視) 5. 買い物能力 6. 簡単な調理能力 | 択一式または観察による判断 |
【特別な医療について】(過去14日間に受けたもの/複数回答可)
| 医療内容項目例 |
|---|
| 点滴管理 |
| 中心静脈栄養 |
| 透析 |
| ストーマ(人工肛門)処理 |
| 酸素療法 |
| 人工呼吸器(レスピレーター)使用 |
| 気管切開処置 |
| 疼痛管理 |
| 経管栄養(胃ろう等) |
| モニター測定(血圧、心拍数、酸素飽和度等) |
| 床ずれ処置(じょくそう) |
| カテーテル管理(コンドームカテーテル、留置カテーテル等) |
【判定基準について】
調査項目は以下3軸で判定されます。
- 能力:本人がどこまで自分でできるか
- 障害や現象(行動)の有無:身体的異常や精神症状など
- 現在提供されている介助内容:他者からどんな支援があるか
問題解決への具体的アクション
- 事前準備徹底
普段の日常生活状況を書き出し、「できないこと」「困っていること」を具体的メモ化する。写真や動画も有効です。 - 家族との情報共有
本人だけでなく家族全員で状況把握し、一致した情報提供体制づくり。 - 専門家相談活用
地域包括支援センターやケアマネジャーへ早期相談し、不明点確認およびサポート依頼。 - 当日の対応準備
リラックスできる環境づくり。無理強いせず普段通り過ごすよう促す。 - 特記事項への注力
困難な点だけでなく改善努力も含め具体的文章化依頼。医師意見書との整合性確認も重要。 - 再申請・異議申し立て対応準備
結果通知後、不満あれば速やかに再申請または審査会への申し立て準備開始。 - 継続的フォローアップ
有効期間中も心身変化あれば速やかに変更申請し適正サービス維持。
全力反論
- 訪問調査は不公平感がある?
個々の担当者によって判断基準が異なるため、公平性欠く恐れがあります。しかし実際には複数名による審議制と主治医意見書併用でバランス取っています。また客観データ活用拡大中です。
- 本人虚偽申告問題
本人が無理して「できる」と言うケース多いですが、それは本人尊厳保持願望表現でもあります。これを理由に厳しく扱うべきではありません。家族との協力関係構築こそ大切です。
- 時間不足
約1時間程度では全容把握困難との指摘があります。しかし事前資料提出および複数回面談可能な仕組み導入検討中です。
- 複雑すぎて分かりづらい
制度自体難解ですが、市町村窓口等相談体制充実化進行中です。またICT活用による説明ツール開発も進んでいます。
- 結果不服申し立て手続き煩雑
確かに手続き負担大きいですが、高齢者福祉向上には不可欠なプロセスとして簡素化検討されています。また代理人利用可能です。
まとめ
訪問(認定)調査は一見すると難解で不安も多いものですが、その本質は高齢者一人ひとりが適切な支援と尊厳ある暮らしを享受するための大切なプロセスです。私たちはありのままの日常生活状況を正確に伝え、自分らしい暮らし方実現へつなげていかなければなりません。そのためには、ご家族との連携と専門機関への早期相談が不可欠です。また、一回限りではなく継続して心身状態変化へ対応していく姿勢も重要となります。
参考文献・引用元一覧
- 「2024年最新版 介護保険の仕組み」 https://up-kaigo.jp/?p=22
- 「初心者向け 介護認定とは?」 https://tayorinosato.com/kaigonintei-application-criteria-guide/
- 「訪問調査スムーズガイド」 https://theotol.soudan-e65.com/support/available-services/certification/nintei-chosa
- 「2025年版 みんなの介護 保険制度解説」 https://www.minnanokaigo.com/guide/care-insurance/

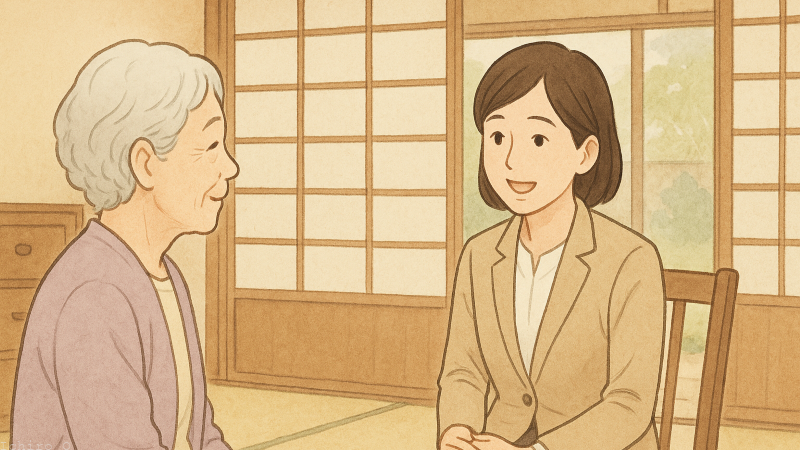

コメント