認知症の悩みを解決するために ~その症状と家族の工夫~
■ はじめに
介護の現場で大きな悩みとなるのが「認知症にどう対応するか」――。
認知症は物忘れ(記憶障害)だけでなく、さまざまな症状が現れます。認知症には誰にでも起こる「中核症状」と、周囲の関わりや環境で悪化・軽減する「行動・心理症状(BPSD)」の二つがあります。これらの症状を正しく理解し、的確な対策をとることで、介護負担や家族のストレスを軽減することができます。
■ 認知症の二大症状:中核症状と行動・心理症状(BPSD)
1. 中核症状とは
中核症状は、脳の神経細胞機能が低下することで直接生じる認知機能の障害です。これはすべての認知症患者に共通して現れる症状で、以下のようなものがあります。
- 記憶障害
ついさっきの出来事を忘れてしまう、食べたこと自体を覚えていない(通常の「老化による物忘れ」とは違い、食事そのものを忘れてしまう)。 - 見当識障害(時間・場所・人物の混乱)
今日の日付や季節、自分のいる場所や帰る道、家族の顔すら認識できなくなります。 - 判断力・理解力の低下
買い物のお釣り計算や食事の用意、会話内容の把握などができなくなります。また、服の着脱や家電の操作など、複雑な動作も困難に。
これらは病気の進行とともに徐々に強くなり、日常生活にも大きな影響を及ぼします。
2. 行動・心理症状(BPSD)とは
「BPSD(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)」は、認知症の患者さんの約8割に現れると言われる精神的・行動的症状。これは本人の脳の障害だけではなく、取り巻く環境や人間関係、その人の性格などが絡み合って生じるため、症状や強さには個人差があります。具体的には以下のようなものがあります。
- 抑うつ(うつ症状)
できていたことができなくなって落ち込んだり、何事にも興味を持てず食欲が無くなる。 - 妄想
家族がサイフを盗んだと思い込む、現実には起きていないことを確信し疑わない。 - 過食や拒食
食事した直後でも「食べていない」と言って何度も食べる、または食事への関心喪失から拒食が現れる。 - 幻覚
「家に小人がいる」などの幻視や、音がしていないのに声が聞こえる幻聴などがある。本人には現実の出来事なので否定すると関係が悪化することも。 - 興奮
怒りっぽくなったり、手が出る、理由もなく興奮した状態になる。 - 徘徊・迷子
家族の目を離した隙に外に出て迷子になることも。無目的に歩き回っているようで、本人なりの理由があることも多い。
これらの「周辺症状」は、医療や介護、環境の見直しで軽くできる場合があります。深刻化する前に、気になる症状があれば早めにかかりつけ医に相談することが非常に重要です。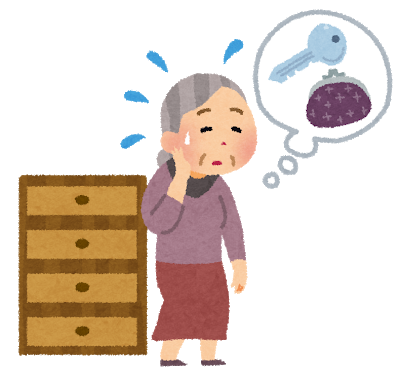
■ アクションプラン:介護の悩みを解決するためにできる行動
認知症による症状を前提として、介護が抱え込まない工夫と具体的なアクションをご紹介します。
- 身近な変化に気づいたらすぐ相談を
物忘れや言動の異変に気付いたら、自己判断せず専門機関へ早めに相談しましょう。 - 正しい知識・対応法を身につける
認知症の基礎知識を家族皆で共有し、BPSDの対応策(否定せずゆったり受け止める、環境調整、ストレス軽減法など)を学ぶ。 - 記録ノートの活用
日常の変化や気付きを簡単に記録。医師へ相談するときの大切な資料になります。 - 支援サービスの積極利用
デイサービスやショートステイ、ヘルパー利用、地域包括支援センター等の行政サービスも活用。 - 家族や介護者自身の負担軽減も意識
一人で抱え込まず、家族内で助け合いや分担、必要であれば専門家のサポートを頼る。
■ 反論:行動プランの限界と現実的な課題
「そうはいっても、現実はそんなに簡単じゃない」という声も多いはずです。
- 家族が遠方在住・仕事で忙しく『気づいてもケアの時間や余裕がない』
- 本人が受診や他人の介入を拒否する
- 行政サービスが十分でない・利用方法が分かりにくい
- 自分自身も心身が疲弊しサポートできなくなる恐れ
また、BPSDの症状は家族や周囲がどれだけ努力しても完全には防げません。認知症に「絶対の正解対応」はなく、家庭ごと個人ごとの工夫や妥協、時に“逃げる”ことも必要――そう考えること自体が介護を続ける上で大切です。
■ まとめ:介護の悩み解決のために最も大切なこと
認知症の中核症状やBPSDの正しい理解・早期相談・支援サービスの活用を通して、家族や介護者自身が「抱え込まない」こと、そして“完璧な対応“を目指し過ぎないことが、悩みを軽減し本人の尊厳も守れる介護の近道です。最初は戸惑いがあっても、少しずつ小さな工夫と支援を積み重ねていきましょう。
合わせて読みたい別の記事:【アルツハイマー 型 認知症】は早期発見が大切。主な認知症の特徴


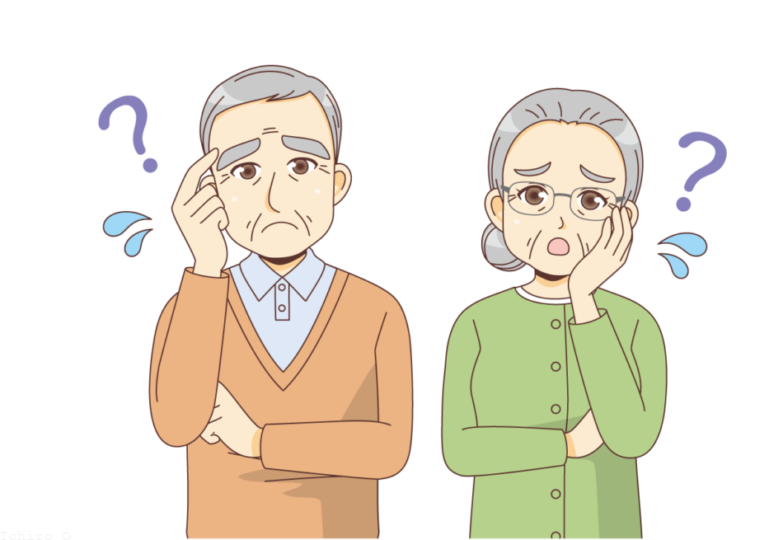


コメント